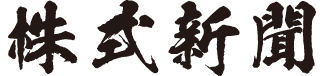FRBの強い意志による「ドル高」継続か? 外為オンライン・佐藤正和氏

夏の終わりに恒例となった「ジャクソンホール」でのパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演が、金融市場全体に大きな影響をもたらした。同議長のタカ派的な発言は、ニューヨーク市場のダウ平均株価を大きく下落させるなど、株式市場や為替市場に大きな影響を与えた。ひょっとしたら金融引締め政策を転換させるのではないか、という希望的観測もあったジャクソンホールでの講演だったが、直近の予想通りタカ派色の強い内容になったようだ。9月はいったいどんな相場展開になるのか……。外為オンライン・アナリストの佐藤正和さんに9月相場の見通しを伺った。
ジャクソンホールのパウエル議長の発言はどう捉えればいいのでしょうか?
パウエル議長の発言のポイントは、「物価の安定を回復するためには、景気抑制的な政策スタンスを一定期間維持することが必要となる可能性が高い。過去の記録は早急すぎる政策緩和を強く戒めている」という言葉に象徴されるように、インフレを根絶するためには、今後も利上げを行い、金利を高い水準でしばらく維持することが重要であることを明確にしました。
インフレを止めるために今後も利上げを続けると宣言したわけですから、市場には失望感が広がり、NYダウ平均株価は1000ドルを超える下落をしました。ドル円も金利上昇によってドルが買われ、1時1ドル=139円にタッチするところまでドル高円安が進みました。
これで焦点になるのが、9月20日-21日にかけて行われる「FOMC(米連邦公開市場委員会)」で、0.5%の利上げになるのか、それとも0.75%になるのか……、という点になります。パウエル議長は利上げ幅については言及しませんでしたが、やはりFOMCまでに発表される「データ次第」ということになるようです。
具体的にはどんな景気指標が注目されることになるのでしょうか?
とりあえずは、9月2日に発表される米国の雇用統計があります。前回(7月)の統計では非農業部門の雇用者数は25万8000人の予想に対して、52万8000人の増加となりサプライズになりました。依然として、米国景気は堅調であるとの憶測からドルが買われました。9月2日に発表される8月の雇用統計では、同30万人の増加と予想されていますが、この予想を上回るようであれば景気拡大=インフレ率上昇、という連想がはたらいて、次回のFOMCで0.75%の利上げが予想されることになります。
そうなれば、米国金利の上昇からドルが買われ円安が進むことになります。逆に予想を大きく下回るようなことになれば、金利の上昇幅は0.5%と判断されて、逆にドルが売られて円が買われることになります。同時に発表される失業率も、3.5%と予想されていますが、予想通りであれば7月と同じく「労働市場は好調」と判断されます。
その他、注目すべき点は「IMS製造業景況総合指数(9月1日)」、「消費者物価指数(CPI)」及び食品とエネルギーを除いた「コアCPI」(いずれも9月13日)などが大きな影響を与えることになります。さらに、ロシアとウクライナの戦争によって、原油や小麦といった資源価格が不安定になっていますが、また以前のように上昇する兆候が現れると、インフレが加速するという発想から利上げ幅が大きくなる可能性があります。
その原油価格ですが、また少しずつ上昇していますが……?
原油価格は一時期1バーレル=85ドルまで下落したものの、ここにきてまた上昇トレンドに入ってきています。9月に入ったことで欧州では秋が近づいてきており、その先には燃料を大量に消費する厳しい冬がやってきます。経済制裁をロシアにかけている欧州諸国にとっては、エネルギー価格の高騰をまともに受ける可能性があります。
もともと今回のインフレは、ロシアが始めた戦争による資源価格の高騰がきっかけだったことを考えると、今後もインフレの勢いが続くこととなり、欧州を中心に対応を迫られることになるはずです。
その欧州中央銀行(ECB)の理事会が9月8日に予定されていますが、そこで前回に引き続いて利上げがある可能性が高いと思います。すでにユーロはドルと同じ価格の「パリティ」を割り込み、0.9914まで売られましたが、ドル高ユーロ安のトレンドは9月も続く可能性があります。
9月は、日本銀行の金融政策決定会合も予定されていますが……?
ジャクソンホールでは、日本銀行の黒田総裁も発言しましたが、相変わらず日本のインフレは商品価格上昇によるものであり、「年内2%または3%に近づく可能性があるが、来年には1.5%に向けて再び減速すると予測している」と述べています。
インフレ退治には動かない、という姿勢を改めて示した形ですが、このまま日本だけがマイナス金利政策やイールドカーブコントロールといった金融緩和政策をとり続けることで、どんな影響が出るのか。長期的に注視していくほかはなさそうです。
日本銀行が簡単に金利をあげられない背景には、金利を上げると保有する国債の含み損によって日銀が債務超過に陥るリスクが指摘されていますが、その他にも銀行から預かっている「日銀当座預金」の残高が563兆円(2022年3月末)に膨張しており、金利が引き上げられれば莫大な利払い額になることが危惧されているためだとする説もあります。いずれにしても黒田総裁の任期が終わる来年4月までは、動きはないと考えていいのではないでしょうか。
9月の予想レンジを含めて教えてください。
9月20日のFOMCまでには、様々な景気指標が発表されますが、その都度、市場はボラティリティ(変動幅)の大きな反応をするのではないかと考えられます。ドル円も1ドル=140円台の大きな節目を突破していく可能性は、ある程度想定の範囲内になっていると考えましょう。9月の予想レンジは次の通りです。
●ドル円……1ドル=135円-141円
●ユーロ円……1ユーロ=134円-141円
●ユーロドル……1ユーロ=0.97ドル-1.02ドル
●英国ポンド円……1ポンド=158円-165円
●豪ドル円……1豪ドル=93円-96円50銭
9月の為替相場で注意すべきことは?
最近の為替市場は、ここ数年分のボラティリティーを短期間に達成してしまうなど、大きく乱高下しています。例えば、この1ヵ月でも1ドル139円39銭の高値を付けた後、1ドル130円39銭まで下落するなど、市場は「過剰反応」すると考えたほうがいいと思います。
また、現在のトレードの主役は「AI(人工知能)」が行っているため、方向性を定めないで淡々と売買していると考えた方がいいかもしれません。良いデータが出れば買い、悪い兆候が出れば売る……。ただ、それが大きく増幅されると考えた方がいいかもしれません。
そういう意味では、トレンドに合わせて追随するトレードを心がけるようにすることが大切かもしれません。ただし、深追いは禁物です。ポジションを少なめにして、市場のトレンドを細かく追っていく。そんな運用を心がけましょう。
(文責:サーチナ)

関連記事
-
10時の注目株=三角もち合い形成中、割り負け感も強い――日華化学
2022/9/1 10:00
日華化学はマーク続行の対象になる。株価は、3月8日の年初来安値677円から6月9日の年初来高値950円にかけて上昇を演じた後は調整足に転じたが、足元では三角もちあいを形成中だ。収れん・・・…続き
-
レーティング情報(目標株価変更・その3)=マツダ、三井物産など
2022/9/1 9:58
◎岡三証券(3段階・強気>中立>弱気) マツダ――「中立」→「中立」、1200円→1300円◎東海東京証券(3段階・アウトパフォーム>ニュートラル>アンダーパフォーム) 三井物産…続き
-
レーティング情報(目標株価変更・その2)=協和キリン、ニチレイなど
2022/9/1 9:57
◎みずほ証券(3段階・買い>中立>アンダーパフォーム) 協和キリン――「買い」→「買い」、3560円→3750円 ダイセル――「買い」→「買い」、1350円→1400円・・・…続き
-
アナリストらがETHユーザーに対しマージ当日は取引避けるよう助言、多数のリスクを指摘
2022/9/1 9:56
イーサリアム(ETH )のマージが近付く中、このイベントによって生じる可能性があるリスクがますます議論されている。暗号資産(仮想通貨)調査会社のコインメトリクスは、明白な危険性の1つとしてDeFi(分散型金融)プロトコルにおける価格のかい離を指摘し、ユーザーに対しマージ当日は取引を完全に控えるよう助言している。…続き
-
レーティング情報(目標株価変更・その1)=NRI、電通グループなど
2022/9/1 9:56
◎野村証券(3段階・Buy>ニュートラル>リデュース) NRI――「Buy」→「Buy」、4600円→4900円 富士フイルム――「Buy」→「Buy」、9500円→1・・・…続き
速報ニュース
-
26日寄り付きの日経平均株価=191円58銭高の3万9364円73銭
11時間前
-
<新興国eye>トルコ6月経済信頼感指数、サービスと小売り、建設のすべてが低下―設備稼働率変わらず
11時間前
-
マーケット早耳情報=話題株の前場寄り前成り行き注文状況―INPEX、ソシオネクス、イオンなど
11時間前
-
<レーティング変更観測>新規・湖北工業/三浦工格上げ、三住トラスト格下げなど
11時間前
-
マーケット早耳情報=主な前場寄り前成り行き注文状況(2)郵船、アドバンテス、みずほなど
11時間前
-
マーケット早耳情報=主な前場寄り前成り行き注文状況(1)トヨタ、三菱UFJ、ソフバンGなど
11時間前
-
26日の東京外国為替市場見通し=ドル・円、159円台後半を軸にもみ合いか
11時間前
-
11時間前
-
島津製、クロマトグラムおよび直接イオン化質量分析計のデータに対応する統計解析ソフトウエア発売
11時間前
-
11時間前