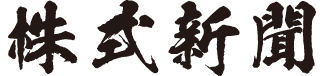海外株式見通し=米国、香港
【米国株】金融緩和は既に進行、半導体巻き返し

米国の主要株価指数は5月に入り堅調に推移し、4月の下落分を取り戻した。15日にはNYダウが1カ月半ぶり、ナスダック総合指数が連日で史上最高値を更新した。FOMC(米連邦公開市場委員会)でFRB(米連邦準備制度理事会)が6月からバランスシート圧縮(量的引き締め=QT)のペース減速を行うと決めたことに加え、米財務省も米国債買い入れ消却を5月下旬~7月にかけて行うとしたこともその原動力だろう。市場がFRBの利下げ観測で一喜一憂する間、実質的な金融緩和は既に進行していると言えそうだ。
他方、物価上昇と景気後退が同時進行する「スタグフレーション」が懸念され始めている。主要株価指数が最高値を大きく更新するには、CPI(消費者物価指数)や小売売上高などでスタグフレーション懸念を払しょくすることが条件となろう。なお、15日に発表された4月の両経済指標は、CPIコアの伸びが前月から鈍化し、小売売上高は前月比横ばいだった。
ウォルマート(WMT)をはじめ、大手小売企業の決算発表を控える中、足元の決算動向ではプロクター・アンド・ギャンブル(PG)のように衛生関連商品など生活必需品を扱う企業が堅調だった。一方で、飲食関連でスターバックス(SBUX)やマクドナルド(MCD)のように強いブランド力があっても物価上昇が業績に響き始めるケースが目立っている。医薬品・医療関連など、よりディフェンシブ度の高い銘柄が物色される可能性があり、肥満症治療薬のほか日本のエーザイ(4523)と認知症関連の治療薬を共同開発しているバイオジェン(BIIB)などが注目される。
生成AI(人工知能)に係る先端半導体関連株も巻き返しの兆しがある。台湾TSMCの月次売上は、直近の4月が前年同月比約60%増となり市場を驚かせた。22日のエヌビディア(NVDA)の四半期決算発表に向けて、生成AIのインフラ(基盤)、ソフトウエアなどへと重点がシフトする展開が見込まれる。データベースでインフラとプラットフォームの両方を兼ね備えたオラクル(ORCL)が有力だ。
【香港株】中国本土個人の配当課税免除に期待
個人投資家が「ストックコネクト(中国本土と香港の株式市場の接続)」を通じて購入した香港株について、中国当局が20%の配当課税を免除する案を検討していることが5月10日に報じられた。香港では配当金が非課税のため、中国本土の投資家と公平に扱うことや二重課税を避けることが目的とみられる。
中国当局の相次ぐ政策を評価して海外投資家の資金流入が続いている。本土と香港に重複上場する銘柄のカイ離が5年ぶりの高水準となるなど、本土株に対する香港株の割安度合いが大きいこともその大きな要因とみられる。4月以降はハンセン指数が日米欧の主要株価指数を大きく上回るパフォーマンスを示している。
ストックコネクトを通じた香港株の売買が拡大することで、直接的な恩恵が見込まれる代表的銘柄が香港取引所(388香港)だろう。4月24日発表の2024年1~3月決算では、本土向け(北行き)取引金額が前年同期比37%増に拡大した。配当課税免除案が決まれば本土から香港向け(南向け)の増加も期待される。足元業績は現物株式と有価証券デリバティブが伸び悩むも、傘下のLME(ロンドン金属取引所)を通じた非鉄金属などコモディティー取引の増加が加速している点は注目される。
高配当利回り銘柄も浮上する。ハンセン指数構成株の中で利回りが高いことで知られる国有企業系銘柄は、予想配当利回り(直近発表の配当額を支払い頻度に応じて年率換算したもの)がおおむね1月下旬から大幅なピークアウトに転じた。予想配当利回りでは1月22日に10%超だった銘柄も、足元で6~7%台となるなど、国有企業系で信用力の高い銘柄が他市場との比較で「特別に異様な」高配当利回りで放置されることがなくなってきている。
※右の画像クリックでグラフ拡大
(フィリップ証券リサーチ部・笹木和弘)
(写真:123RF)
関連記事
-
【株式新聞・正午版】アルー、中期的に上値トライ――営業強化で新規顧客開拓
2024/5/16 12:00
アルー(7043)は800円近辺で底堅さがある。中期的に上値に挑む展開が予想されよう。 同社はビジネススキル研修、マインド研修、語学研修など、法人向け人材教育事業を手掛ける。今12月期の第1四半期(・・・…続き
-
リベロが急反発――1Q決算好調
2024/5/16 11:44
リベロ(9245)が急反発。15日大引け後、今12月期の第1四半期(1~3月)決算を発表し好調だった。 第1四半期の連結売上高は11億1100万円(前年同期比33.9%増)、営業利益は3億1200万・・・…続き
-
リクルートHが急伸、国内人材サービスの好調を材料視
2024/5/16 10:24
リクルートホールディングス(6098)が急伸し、上場来高値を付けた2021年11月以来となる7500円台を回復した。15日に発表した前3月期の連結決算が好感された。 前期の調整後EBITDA(※)は・・・…続き
速報ニュース
-
26日の東京外国為替市場見通し=ドル・円、153円台でもみ合いか
25時間前
-
<新興国eye>日本、カンボジアに円借款を供与―南部経済回廊整備を支援
25時間前
-
<新興国eye>トルコ7月経済信頼感指数、サービスと小売り、建設のすべてが低下―設備稼働率は上昇
25時間前
-
<レーティング変更観測>新規・関西ペ/IDOM格上げ、日産自格下げなど
25時間前
-
<きょうの材料と有力銘柄>東北・記録的大雨で災害警戒―関連株をチェック
25時間前
-
株式新聞プレミアム=シンメンテH、トレンド転換―業績安定感も抜群
25時間前
-
25時間前
-
25時間前
-
シルバライフ、エームサービスおよびグループ会社に調理済み冷凍パック惣菜提供
25時間前
-
25時間前